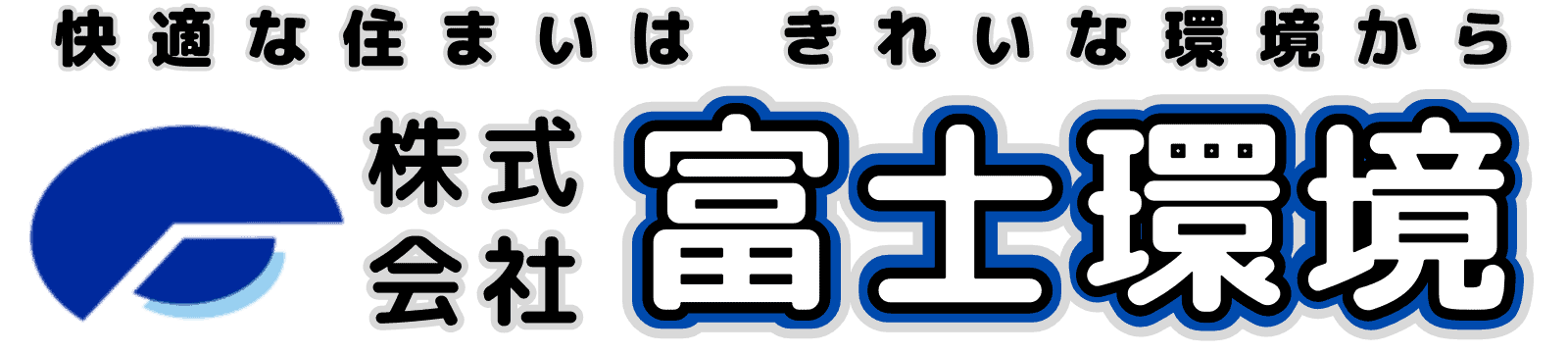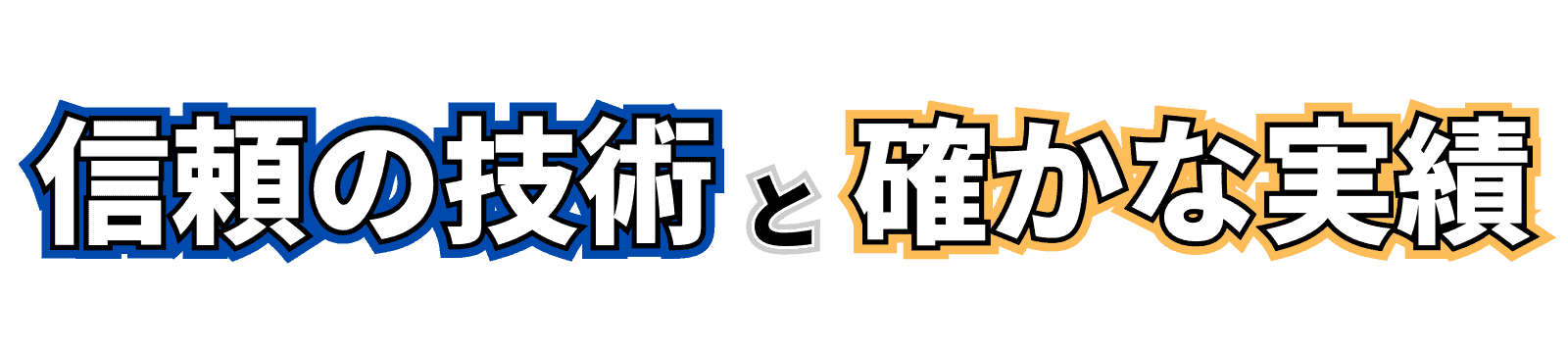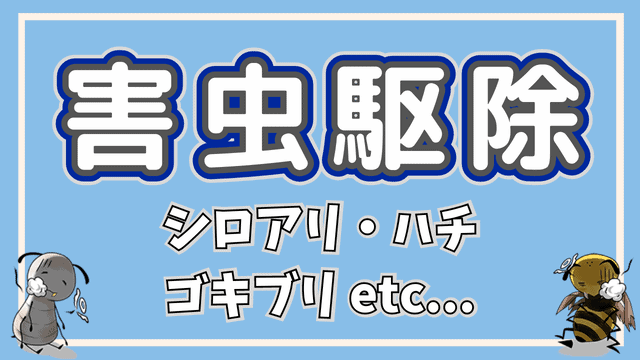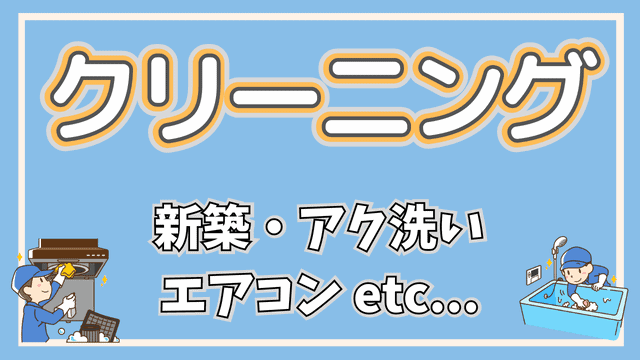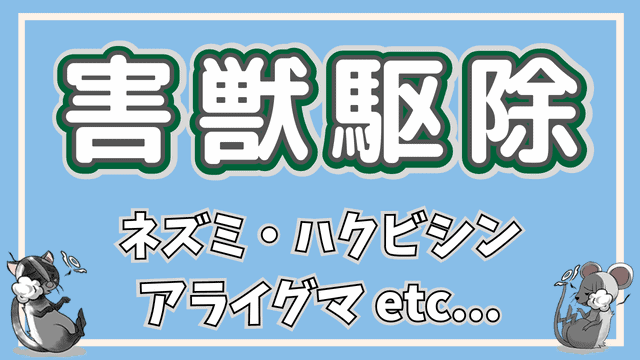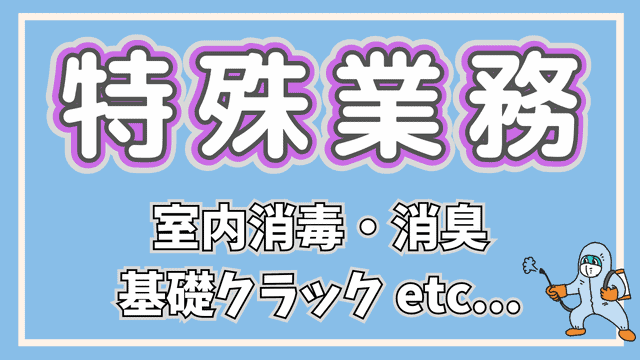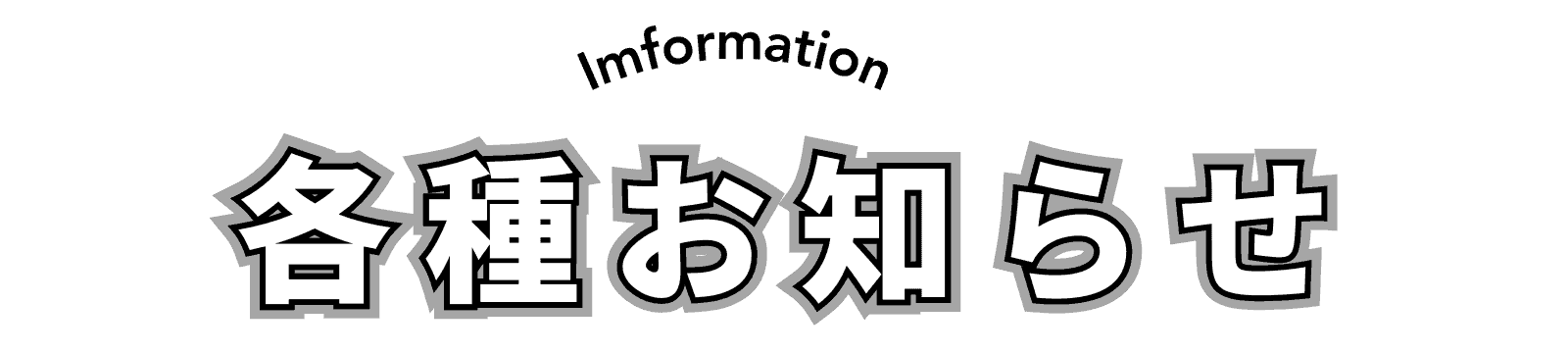当社富士環境は、1986年に埼玉県宮代町で創業して以来、多くのお客様・お取引先様に支えられ、シロアリやゴキブリなどの害虫防除、ねずみをはじめとする害獣駆除、ハウスクリーニング等のサービスを行っております。
創業以来、積み重ねてきた技術と信頼でお客様のご要望にお応えいたします。
スタッフ一同 「 お客様の気持ちになって 」 常に迅速な対応と誠実な施工を心がけております。
害獣・害鳥・害虫にお困りの時は、お気軽にご相談ください。
わたしたちができること
私たちの仕事は、薬剤を撒いたり安易に工事を請け負うことではありません。
害虫駆除・害獣駆除のプロとして、知識や技術の研鑽に励み、優れた技術を適正な価格で提供できるよう努めています。
お客様が安心して弊社の各種サービスをご依頼いただくためにしっかりとヒアリングを行い、お客様のお困り事や悩みと真摯に向き合い、プロとして適切なご提案を申し上げております。
弊社へのお問い合わせは、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
お急ぎの方は、お電話での対応をさせていただいております。
電話対応窓口:0120-34-9927
対応時間:8:00〜18:00(日・祝除く)